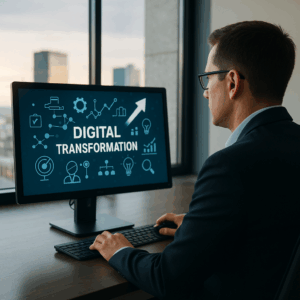こんにちは。代表理事の本田です。
時代が変われば、技術も変わる。そして、我々ITコーディネータに求められる役割もまた、大きく変わろうとしています。
昨年、「ITコーディネータプロセスガイドライン(PGL)」の最新版、PGL4.0が公開されました。
我々の支援活動の指針となっていたPGL3.1からのアップデート。その内容は、ベースは今までの考え方を踏襲しつつも、現在の社会・経済環境を映し出すような、非常に象徴的かつ本質的な変化が含まれています。
特に注目すべきは、以下の3点ではないかと思います。
まず1つ目は、「IT経営」から「デジタル経営」へのシフトです。
これまでのPGL3.1が「ITの利活用による経営改革」に軸足を置いていたのに対し、PGL4.0は「データ駆動型社会で価値を実現するための方法論」へと大きく舵を切りました。
言い換えれば、単なるIT導入支援を超えて、データとデジタル技術を活かして新たなビジネスモデルと顧客価値を生み出す「デジタル経営」の支援が、改めて明確に語られているいうことです。
2つ目のポイントは、「反復型プロセス」と「BizDevOps」の導入。これまでは比較的ウォーターフォール型に近いモデルに見えていた部分もありましたが、PGL4.0では「デジタル経営成長サイクル(C1)」と「価値実現サイクル(C2)」という2つのサイクルを中心とした反復型プロセスを採用。外部環境の急激な変化に迅速に対応することが求められるVUCAの時代において、ビジネス、開発、運用が一体となって価値を創出し続ける「BizDevOps」の思想がより重要視されています。
そして3つ目が、「顧客価値の創出」と「組織学習」、そして「セキュリティ」の明確な位置づけです。特に、PGL4.0では「提供価値検証プロセス(P6)」が新設され、成果が本当に顧客価値につながっているかを継続的に見直す仕組みが導入されました。また、新たな共通基盤(CB)には、「組織学習」や「セキュリティ」といった継続的・横断的な取り組みが不可欠であるとの認識が明記されています。
さて、ここで少し話は逸れますが、今、私たちが強く感じているのは生成AIの急激な進化と普及です。
ChatGPTのようなツールが登場してからというもの、「人間の仕事とは何か」、「知的生産とは何か」という根本的な問いが突き付けられています。
これまでのIT活用では想定されなかったレベルで、AIは経営とITの関係性そのものを再定義しようとしているように見えます。
そうした中、改めて「中小企業とは何か?」という問いにも向き合う必要があるでしょう。
法的には資本金や従業員数で定義されていますが、実際にはその枠にとどまらない企業像が次々と現れてきています。
一人でAIを活用し、グローバルな事業を展開する【ユニコーン】もどきの小規模企業も、近い将来珍しくなくなるかもしれません。
今後の少子高齢化による人手不足は避けがたく、多くの企業がより小規模化していくことも想定していかない流れの中で、従来の「中小企業支援」のあり方もまた見直しが求められてくるのではないかと思います。
PGL4.0には、AI活用に関する記述も盛り込まれています。
つまり、AIも含めたデジタル技術をどう組織に取り込み、持続的な価値創出と組織の学習をどう仕掛けるか ――それが今後のITコーディネータに課せられた新たなテーマなのではないか?という気がしています。
私たち、みちのくIT経営支援センターでは、これからの「デジタル経営」時代に対応した支援のあり方を、地域の仲間と共に模索し続けていきます。
あなたも、ITコーディネータとして、新しい時代の経営支援を一緒に考え、我々と共に活動してみませんか?